 |
 |
 |
− 真言宗中国開教史(一) −
日本仏教中国開教の発端
明治六年 小栗栖 香頂(おぐるす こうちょう)中国開教を目指して北京に至る
松下隆洪(平塚市 宝善院住職) |
        |
|
■ 小栗栖(おぐるす)という僧の生まれた村 ■
ことの発端はこういうことだった。
西郷が征韓論にやぶれて野に下った年の明治六年七月。浄土真宗東本願寺派の僧、小栗栖 香頂(おぐるす こうちょう:1831−1905)は、日本仏教を中国に布教することと、仏教を通じてイギリスをはじめとするキリスト教帝国主義に反対するアジア仏教同盟設立の大志を抱いて長崎を出帆した。
それまで、つまり明治維新に至るまで、大方の日本人にとって「思想」とか、そういった大義名分は「唐」(もろこし)を通じてやってくるものであった。
それが旧体制が倒れ、新しく明治政府ができたとたん、こんどは逆に日本人が「唐」(もろこし)へ「思想」を運びたくなった。これは明治維新というものを知る上に、すくなからず一つの示唆を示しているといえないだろうか。彼は真宗の僧侶だが、真言宗の大陸開教も彼から出発しなければならない、いくつかの理由がある。その理由はおいおい後述する。
小栗栖(おぐるす)という苗字は、日本人の姓でもたいへんめずらしい。「日本姓氏家系辞典」で調べると、「小栗栖」という地名は全国に二つあり、そこから姓も出るとある。明智光秀が秀吉にやぶれ、逃れる途中、土民に謀殺された村として知られる京都郊外の小栗栖と、もう一つ伊勢にある。
私はこの人間のことがたへん気になっていたので、ぜひ一度この人物の生まれた村をたずねてみたかった。手もとの資料ではそれも分からず、そのままほったらかしになっていた。今度この稿を書くにあたって、どうしても一度そこを訪れたくて、最近、東本願寺を訪ねてみた。(本稿執筆当時)
あんに相違して彼の出身は九州の大分であった。
大分県大分郡中戸次村(なかへつぎむら)三二二番地、真宗東本願寺派妙正寺。現在の大分市中戸次にあたる。東本願寺にある僧籍簿には、彼がこの妙正寺に明治十二年五月まで住職をしていたとある。
中戸次は別府湾に注ぐ大野川が、長曽我部信親の墓がある洲鼻のあたりをすぎて匚の字形にまがる、ちょうどその匚の字にかこまれたあたりの寒村である。現在の大分駅から車で約二十分。九州特有のおわんをふせたような小高い山と、いたる所けずられた赤い山はだ、プラスチックの看板、原色のビニールトタン屋根、いまではみなれた日本の風景である。大野川沿いに発達した昔の街道は、今は国道十号の裏にかくれ、ひなびた街道沿いに「小栗栖香頂 生誕の地入り口」と白地にかかれた、いささかふつりあいの看板をとうして妙正寺の鐘楼門がみえた。
小栗栖香頂という人間が、いったいどのようなところで生まれたのだろうかと長年想像をしていた私は、その山門をくぐった時「ああーこれは古い風景だ」と思った。本堂はたぶん江戸時代の建築だろうか、式台を構えた庫裡がみえる。時代的にはそんなに古くは無いのに私がそう思ったのは、年を経た木造建築が持っている、特有の黒さのせいだっただろうか。あるいは所々に生えている雑草のせいだっただろうか。そこが小栗栖香頂という変わった姓を持つ、真宗僧の生まれた所であった。
それまでの日本人にとって「思想」というものは、つねに海のかなたから異国人が持ってくるものであったし、あるいは海のかなたへとりにでかけるものでもあった。純粋に日本人が「思想」を海の彼方へ、まきちらしに行ったなどは、それまでなかったことであった。
それが明治維新を迎えたとたん、今度は思想を運び出そうとする日本人が現れた。運びこまれたものを、運び出そうとする、この価値の転換が明治維新の一つの側面であったというなら、小栗栖(おぐるす)という、今までほとんど無名に近かった一人の真宗僧侶のしたことは、ある意味で「明治維新」そのものであったといえよう。日清・日露戦争へとつづいていく、その後の日本の、これは象徴ともいうべき人物でもあった。つまり「思想」を海の彼方へ運び出そうとするということでだ。それが明治六年であったといえば、西郷が征韓論にやぶれて鹿児島に下った年のできごとだ。この二つの事件のあいだに、いったいどのようないきさつがあったのか、ひどく興味をそそられたのである。
私がお会いした小栗栖公運師は香頂から数えて四代目、妙正寺の十六代目の住職となった人である。この人の祖父が香頂の次弟に当たる人であった。香頂には二人の弟と一人の妹があったが妙正寺を継いだのは、香頂の息子の厳龍ではなく、次弟の大 であったからである。 であったからである。
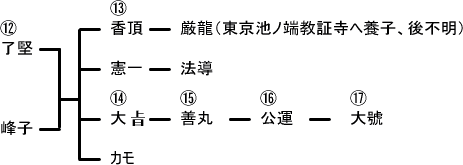
香頂の家系にはやはりおもしろい人物が多い。上の弟の憲一は、香頂の死後彼の略伝を作った人物であるが、号を布岳(ふがく)といって絵を書いたり、一時は宮内省へ勤めたこともあったらしいが、後には京都の西京中学の校長となった。この人は真宗の僧侶にはならなかったようだが、明治三十二年、朝鮮・京城本願寺別院の建築に朝鮮皇帝が、寄附をしてくれた、その謝礼の副使として渡鮮したりしているから、香頂の宗団での活動を、いろいろな意味で側面から援助してくれていたのだろう。そういうことでは香頂の跡をついで住職となった次弟の大 も、やはり香頂の行動を側面から援助するつもりだったらしい。香頂が死亡したのは明治三十八年三月十八日だが、彼が妙正寺の住職を辞任したのは、それよりずっと前の明治十二年のことだからである。弟の手助けを頼りに海外活動のために早く隠居したのであろう。 も、やはり香頂の行動を側面から援助するつもりだったらしい。香頂が死亡したのは明治三十八年三月十八日だが、彼が妙正寺の住職を辞任したのは、それよりずっと前の明治十二年のことだからである。弟の手助けを頼りに海外活動のために早く隠居したのであろう。
香頂という人は、子供のときから教育にしても、当時としては十分すぎるほどの教育を受けることができたし、そういう父親にも恵まれていた。こういう環境は、終生彼につきまとったようである。彼は当時としては押しも押されぬ一流のインテリであった。彼の無謀にも思える中国開教も実は、非常に知的な生産活動が迎えた、一種の自然発火のようなものだったといえよう。そういう一風変わった人間の行動を、まわりから援助するような人間たちが、どんな片田舎にもいたのが、どうも明治という時代でもあったらしい。
お話を伺った公運師の書斎には、香頂の古ぼけた油絵の肖像画がかかっている。板にかかれた古い油絵としてはめずらしいものだが、これは残念ながら香頂の真面目をとらえていないように見える。
こういう人物の顔はやはり異相である。「小栗栖香頂略伝」(以下略伝)に彼の写真が二枚のっているが、眼が特に鋭い。それがただ鋭いのではなく、武術に八方眼というのがあるが、あれに近い。どこを見ているのか分からないような、范洋としているが、それでいて鋭い。そうしておいて、どこかでニヤリと笑っているような所がある。状況に全くボルテージを上げているくせに、フッと離れているような彼の行動はそういう所から来ているのかも知れない。
香頂が生まれたのは、天保二(1831)年の八月四日というから、吉田松陰とは一つちがいである。生まれた月も同じである。つまり小栗栖香頂という人物は、攘夷論と開港論、幕藩体制の崩壊から新国家の成立という、日本の最も革命的動乱期に生まれ育った人物であった。大塩平八郎の乱から日露戦争まで見てきた人の眼とは、こういうものなのだろうか。あのフッと離れているような眼は。
そういえばこの人物にはそういう所がある。真宗には幕末期、黙霖という有名な勤王僧がでている。黙霖は私生児の上に、聾唖者であったというが、熱烈な勤王僧として吉田松陰や西郷と心中した僧月性などとも親しかった。同宗からそういう人物も出ているくらいだし、彼自身、京都の高倉待従永胤という、れっきとした公卿の家から嫁をもらうほどの勤王僧でもあったのに、幕末には彼はほとんど勉学にあけくれ、何もしていないのはどういうことなのだろう。見ようによっては、彼は新国家が成立するまで何もしなかったといって過言でないのだ。
『略歴』にはその間のことをこんなふうに書いている。
「桜田大老の変あり、五条一揆の乱あり、魯艦は対州を、英艦は鹿児島を、仏艦は長州を砲撃し、七卿脱走、浮浪横行、海内鼎の沸くが如し。長公(香頂)いわく、我等方外宜しく浩然の気を静養すべし、他日報国の機会あらんと。終歳読書、門外の事をとはず」
とある。
香頂が明治維新を迎えたのは三十八歳の時であるが、それまでこの男は学問ばかりして「門外の事をとはず」という生活をしていた。彼が本願寺の中で政治的な頭角を現したのは、明治二年の宗名恢復運動がはじめてである。それまで学問ばかりしていたから、それじゃ学者だったのかといえば、この事件以降の彼の政治手腕は抜群だし、まるで目を見はるような変身ぶりである。その間の彼は、国家ができあがるまで、九州の片田舎で昼寝をしていたとしか思えないほどだ。なにしろ「終歳読書、門外のことを問はず」というのだから。ようやく新国家ができあがると、「どれ、どれ、どんなふうにできたかな?」と京都に出てきた。さてそれからがものすごい。
明治元年三月に本山からしかるべき役職を与えられ呼び出された香頂が、中戸次の片田舎からでてきてはじめて手がけたのが、「宗名恢復運動」であった。これは明治二年、京都府令が「真宗をして自今一向宗と称せしむ」と命じたことによる事件であった。大隈重信と会見して、この事件を解決し、宗名を救ったのは全く彼の働きであった。それから明治三十八年に七十六才で死ぬまで、まともに自坊にいたのは病気の時くらいだろう。まるでブルドーザーだった。
これほど政治的な人物が、歴史も人間もいちばん過激になる幕末動乱時代に、それだけの知識もバイタリティーもあるのに、何もしなかったというのはどういうことなのだろうか。
考えようによっては、たとえば彼が所属した東本願寺が、西本願寺が幕末期、勤王方として経済的な援助を倒幕派にしていたのに対し、自分が所属する東本願寺が幕府方だったからだろうか。己の思想は倒幕派であったが、所属する教団組織に対する彼の保身術だったのか。そうはいっても国家が成立するまで満を持して己を律するとは、こんな日本中が気違いになっているような時代、とても普通の人間にできる芸当ではない。やはりとんでもない人物なのだ。
ところでこの人はいよいよおもしろい。というのは最初に彼の名前を聞いた時、明智光秀の殺された小栗栖村となにか関係があるのかと思ったのだが、やはりそうだった。
公運師の語るところでは、小栗栖家の先祖は小栗栖大善光豊といって、光秀が謀殺された小栗栖村の五千石の領主であったという。光秀から光の字をもらい光秀の家来であった。それが主君が信長を殺し、結局は主君・光秀も秀吉にやぶれた。主君が殺されたからといって秀吉につかえるわけにもいかず、豊後に下って出家したのが妙正寺の開基であったという。
小栗栖村一ヶ村で五千石もの禄高があったのか、あるいは光秀が小栗栖村で殺されたのは戦闘に破れ近江へ逃げる途中、先祖の大膳光豊を頼って小栗栖へ来たのであろうが、そこで光秀が謀殺された時、光豊はどういう立場にあったのかまで論ずる余裕はないが、とにかく彼の血のどこかに、その大善光豊という戦国武将の血がまじっているということだろう。
香頂の先祖が明智光秀の家臣であったことと、彼の大陸行きと何か関係があったとは思えないが、中国での彼の日記や著述したものの中にもそれに類するものはなにもない。しかし、子供の頃から当然、自分の先祖のことは父親からも云いづたえに聞いていただろうし、そういうことが全く彼の行動に原因しなかったはずもなかろう。おもしろいといえばこういうこともある。
香頂という人は一種のメモ魔である。彼の『略伝』を作った憲一の調べたものによると、香頂が生前書き残した著書・遺編の数は二十一部合計二七〇余巻にのぼったという。
そのうち『八洲日歴』という彼の日記が一六四巻、『蓮舶詩歴』という漢詩集が十巻、その他二十数部にのぼる遺編をあわせると膨大なものになる。なにしろわずか一年の中国滞在中に四冊の著書を書き、そこらじゅうの名僧高僧に悲憤慷慨の書を呈しまくった人物だから、中風で死ぬ三日前まで不自由な体をおして、弟子に日記を口述筆記させるくらいはあたりまえだったというわけである。だから憲一も「略伝」の中で「長公(香頂)の大帰(明治三十一年病気で東京から妙正寺にもどったことを指す。以後彼は死亡するまで公的な場からはしりぞいたので大帰といったもの)は殆ど平生の著書終結の為め、故らに東京を辞するに似たり」といったくらいである。それほどのメモ魔である彼が、先祖のことについては何も書いていない。
香頂の著書に『天恩広大』という木版ずりの十頁ほどの小冊子がある。奥附は明治二年十一月の版になっているから、その前年の神仏分離令から、大教宣布による廃仏毀釈にまたがる時期に出版したものである。
この本、『天恩広大』というから、時期的にもいかにも朝廷を賛える書物のようにみえるが実際は、いささか趣を異にしている。
新国家はできたものの明治政府は、国民のあいだに「将軍様よりまだ偉い人がこの国にいたという」、政府として笑えぬような冗談がでるほど天皇に無知であったため、これを克服するためまず明治元年四月に、「神仏判然令」を出し東照権現(家康)など仏教語を神号とすること、仏像を神体とすることなどを禁止した。これに応じた京都府庁は、真宗の消息中にある本地垂迹の説を削除するよう命令した。このときに出版したのがこの『天恩広大』であった。
奥附に「敢テ之ヲ天下ニ公ニスルニ非ズ、ヒソカニ同社ノ諸君ニ示スノミ」と記されたこの本は、教団が直面していた政府の仏教弾圧政策に対抗して香頂が本書を出版した事情をよく示している。
内容は
一、未来ノ禍復ヲ説テ愚民ヲ誑惑スル事
一、 神仏判然ノ事
の二つから成っていて、政府が当時矢つぎばやに出した対仏教政策に対する論評である。
その中で香頂は大要次のようなことを云ってのけている。
「仏教では三世の因果を説いているが、未来の禍福を説いてはいけないという朝廷からのお達しだが、これは仏教のことをさしているのではないのだろう。朝夕、そういうことをわれわれは信者に説いているが、別にこれといったおとがめもないのだから、さしずめこれは仏教以外の外道のことをいっているのでしょう」
「朝廷が寺院に対する法律を作られたのは、寺院のために筋を考えられてのことで、決して仏法を廃するといったことではないでしょう。それだったらわざわざ寺院のために法律などを作る道理がありません。まことに朝廷の天恩の広大なることを我々は感載すべきです」
「神というものは仏によって現ずるもので、仏を離れて神というものはありえない。これは仏教の本地垂迹の定説であるが、最近の神仏判然というのは一見仏教の説を否定するように思えるが、朝廷の考えられるのはそういうようなことではないと私は考える。さしずめこれは仏につかえることと、神につかえる作法が混雑しないように、神仏判然と申されたに相違ない」
『略歴』によると、上記のような趣旨の文書を密かに印刷しておいて、後に彼は京都府庁に知事をたずねて「歴代の天皇の詔勅にも、歴然としてでていることである。今の朝廷がこれを廃するのは先の朝廷をはずかしめることにはなりはしないのか」といって逆に府庁をおどしている。そして「此れより判然の処分やや寛なるに似たり」となったとある。 |
|
|
|
|